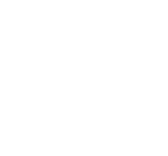 今月の
今月の
特集

2023.6.1
Ourおせっかいのつどい
| 私たちの一歩が、未来をつくる
4月29日を中心に、各地のMyおせっかい推進委員会や「Ourおせっかいのつどい」実行委員会、各支部の青年が新しい仲間を誘い、社会に役立つ活動を行った。九州ブロック、山陰地区、東京都・神奈川県・埼玉県と近畿ブロック、福島県の活動を紹介しよう。
- CASE.1—【九州ブロック】
“共生社会”。その実現のために私たちができること
―障がいへの理解を深める講演・ボッチャ体験…続きを読む - CASE.2—【山陰地区(島根県・鳥取県)】
“他人事にしない”心を伝え、地球の未来を守ろう
―海岸清掃活動…続きを読む - CASE.3—【東京都・神奈川県・埼玉県・近畿ブロック】
一人ひとりのアクションで、救われる命がある
―献血広報活動・献血のつどい…続きを読む - CASE.4—【福島県】
ママと子どもの笑顔が、地域を明るく!
―いろんな人とふれ合って、元気になってほしいから…続きを読む - MESSAGE—(青年部部長)
すべての活動に、新しい仲間と参加しよう!
―全国各地で青年を中心に、小さな子どもから親世代の人まで、…続きを読む
“共生社会”。その実現のために私たちができること
【九州ブロック】
障がいへの理解を深める講演・ボッチャ体験
◆ REPORT ◆
内閣府発表の「令和4年版障害者白書」によると、日本には2018年時点で436万人の身体障がい者が生活している。
九州ブロックの青年たちは、多くの人に障がいへの理解を深めてもらおうと、長年、障がい者スポーツに携わってきた「一般社団法人 久留米市総合型SC桜花台クラブ」(以下、桜花台クラブ)のクラブマネジャーである井手浩さんを招き、講演と障がい者スポーツ「ボッチャ」の体験を行った。
 共生社会とは何かを伝える井手さん
共生社会とは何かを伝える井手さん
 参加者たちは障がいについて深く考えさせられた
参加者たちは障がいについて深く考えさせられた
桜花台クラブは、福岡県を中心に障がい者スポーツの普及事業を行っている団体で、霊友会は、「ありがとう こだま 基金」でその活動を支援している。井手さんは、「障がいのあるなしに関わらず、誰もが安心して暮らせる“共生社会”を実現することが障がい者支援の大きな目標。そのために必要なことは、障がいに関心をもつ人を1人でも多く増やし、私たちの日常生活や社会の中に潜むさまざまな〝生きづらさ〟を取り除いていくこと」だと教えてくれた。
この日集まった参加者1人ひとりが、今日学んだことを身のまわりの人たちに伝えていこうと動き出した。
 「ボッチャ」体験ではチームに分かれて真剣勝負!
「ボッチャ」体験ではチームに分かれて真剣勝負!
 子どもから大人まで、みんなが学んで楽しめる1日となった
子どもから大人まで、みんなが学んで楽しめる1日となった
参加者インタビュー
| わたしにもできる。伝えること

【福岡県 西川史栞さん・S.Kさん 高校3年生】
西川 今日は、最近導いた会員のSさんと一緒に参加しました。
私は今まで、障がいのある人に対して、大変そうだなってイメージしかなかったんです。でも講演で、夢や目標に向けて努力して、社会で活躍している障がいのある人たちの姿を映像で見ることができて少し考えが変わりました。むしろ壁をつくっているのは、何も知らない自分なんじゃないかって感じました。
S 私もそうですが、オリンピックは見ても、パラリンピックは見ない人って多いと思うんです。でも、今日の講演でパラリンピアンが活躍している映像を見て、あんなに速く走ったり、高く跳んだりする姿に、とても勇気をもらいました。
私はこういう場に参加するのは慣れていなくて不安もあったんですけど、障がいや社会福祉について真剣に学び、自分にできることを見つけようとしているみなさんの姿に刺激をもらいました。
西川 こうやって、一緒に学んだり、一緒に体験したりすることで、同じ思いの人が増えていくんだなって感じました。今日学んだことを、1人でも多くの人に知ってもらえるように、Sさんと一緒にまわりの人に伝えていきます。
=====================================================
| 幼かったときの自分を振り返って

【福岡県 N.Aさん 20歳】
高校時代の後輩に誘われて、霊友会のこともよく分からないまま参加したんですけど、来て本当に良かったです。
井手さんの話を伺って、身体障がいのある人にとって何が不便なのか、私たち健常者がそれを学んで、障壁になっていることを取り除いていく。その重要性を感じました。私は幼い頃、体が弱くて入院生活をしていました。その中で大きな不自由なく生活できていたのは、まわりの人が私にとっての不便を取り除いてくれたからだったんだと、今日、あらためて気づかされたんです。
実は今、保育士を目指して専門学校に通っているんですけど、先日のある授業で、身体に障がいのある子どもの保育について学ぶ機会があり、自分でもいろいろと調べていくうちに、そういう子どもたちと深く関わっていきたいと思うように。そんな中で、今回のつどいに参加して、有意義な時間を過ごすことができました。
かつてまわりに助けられた自分だからこそ、子どもたちと向き合い、寄り添っていけると思うんです。私1人の力は小さいけど、その一歩を大事に、まわりの人の力になれる保育士になります。
※写真はイメージです。本文の登場人物とは関係ありません。
“他人事にしない”心を伝え、地球の未来を守ろう
【山陰地区(島根県・鳥取県)】
海岸清掃活動

◆ REPORT ◆
安価で、安全で、私たちの生活を便利にするプラスチック。しかし、それがごみとして海に流れ出ると、話は一変する。海の生態系に悪影響を及ぼし、地球の未来すら脅かすという話を、耳にしたことがある読者もいるだろう。
毎年、海に流れ出るプラスチックごみの量は、世界で約800万トン。その7~8割が、私たちの暮らす街から雨などで川を伝って流れ出るという。2050年の海には、魚よりもプラスチックごみの量が多くなるという予測もある。
そんな「海洋プラスチックごみ問題」に対して、以前から四国ブロックの青年たちが取り組んできたが、今回、中国ブロック山陰地区の青年たちもこの問題に着目した。
島根県出雲市多伎(たき)町に位置する「キララビーチ」。コバルトブルーに輝く遠浅の海は、絶景が望める名所で、サーファーや海水浴を楽しむ人たちに人気のスポット。ところが、その海岸沿いには、海から打ち上げられた漂着ごみがたくさんあるのだ。「Ourおせっかいのつどい」を通して、この問題を他人事にせず、一人ひとりが意識を変え、行動に移す大切さをまわりの人に伝える。そんな仲間の輪を広げようと、4月23日、海岸清掃を行った。
 前田康喜青年部部長も駆けつけ、子どもも大人もみんなでOurおせっかい
前田康喜青年部部長も駆けつけ、子どもも大人もみんなでOurおせっかい
 広いビーチを手分けして清掃した
広いビーチを手分けして清掃した
 砂の中に埋もれたごみも見逃さない!
砂の中に埋もれたごみも見逃さない!
青年を中心に、子どもから大人まで、家族連れで50人以上が参加したこの日。大阪から前田康喜青年部部長も駆けつけた。みんなで力を合わせて清掃に励み、1時間弱の活動で多くのごみが集まった。
その後は場所を移してつどいを開き、「海洋プラスチックごみ問題」への理解を深めるクイズに挑戦し、活動して感じたことを話し合った青年たち。その実感を、これからたくさんの人に伝えていこう!と誓い合った。
 1時間弱の活動で、こんなにたくさんのごみが!
1時間弱の活動で、こんなにたくさんのごみが!
 つどいではクイズを取り入れ、海洋プラスチックごみ問題を学ぶ
つどいではクイズを取り入れ、海洋プラスチックごみ問題を学ぶ
参加者インタビュー
| 毎日のちょっとした心がけから

【岡山県 N.Sさん 22歳】
私は島根県の出身で、今は岡山県で一人暮らしをしながら医療系の大学に通っています。コロナの影響で帰省もあまりしていなかったので、今回、島根の仲間に声をかけてもらい、いい機会だなと思って参加したんです。風が強くて大変だったけど、みなさんと一緒に活動して清々しい気持ちになりました。
キララビーチには、昔から友達と遊びに来ていました。漂着ごみがあることは当時から知ってはいたんですけど、じっくり見たのは今日が初めて。正直、こんなにあるんだ!って驚きました。パッと目につくごみだけじゃなくて、砂の中に埋まっているごみもたくさんあったんです。
プラスチックって、普段、いろんな物に使われていますよね。だから、毎日のちょっとした心がけが大切だなと今日のつどいで感じました。きちんと分別して資源ごみとして出すのはもちろん、そもそも、なるべくごみを出さないように、プラスチック製品は必要な分だけ使うようにする。大学でも環境問題について学ぶ機会は多いけど、学ぶだけで終わりにせず、行動に移していこうと思いました。
コロナ禍以降、友達をつどいに誘ったり、霊友会の教えを伝える機会も少なくなっていました。今日学んだこと、感じたことを友達にも伝え、社会の問題を他人事にしない仲間の輪を広げていきます。
一人ひとりのアクションで、救われる命がある
【東京都・神奈川県・埼玉県】
献血広報活動
【近畿ブロック】
献血のつどい

輸血に使用される血液は長期保存も、人工的に造ることもできないため、持続的に献血協力を求めなければならない。病気の治療などで輸血を受けている人の割合は高齢者が多く、このまま少子高齢化で献血可能な若い世代の人口が減少していくと、安定的に血液を供給できなくなる恐れがある。
私たちの、そしてこれからの世代にかかわる問題を、多くの人に知ってもらい、アクションを起こしてもらいたい―。東京都・神奈川県・埼玉県の各都県ではそれぞれ献血と、献血バス周辺の街頭で道行く人に献血への協力を呼びかけた。近畿ブロックでは献血と、日本赤十字社による講演、参加者のつどいを実施した。各地で活動に取り組んだ青年たちの声を紹介する。
 足を止めて話を聞いてくれる人も。思いを伝え、協力を呼びかけた(東京都)
足を止めて話を聞いてくれる人も。思いを伝え、協力を呼びかけた(東京都)
 日本赤十字社による講演。献血の現状を詳しく学んだ(近畿ブロック)
日本赤十字社による講演。献血の現状を詳しく学んだ(近畿ブロック)
 大型連休初日、心配された天候も晴れ、元気に呼びかけ(神奈川県)
大型連休初日、心配された天候も晴れ、元気に呼びかけ(神奈川県)
 若い世代からアクションを!自分たちも率先して献血(東京都)
若い世代からアクションを!自分たちも率先して献血(東京都)
 子どもたちも一緒に。みんなでできる社会貢献だ(埼玉県)
子どもたちも一緒に。みんなでできる社会貢献だ(埼玉県)
◆ 参加者の声 ◆
神奈川県 Oさん(30 代・男性)
一緒に献血を呼びかけた子どもたちに負けないように、一生懸命声を出しました。活動終了後、日本赤十字社の方から「いつもより多くの方に来ていただけました。ありがとうございます」と言われ、お役に立てて良かったと実感。私が幼い頃、よく献血に行っていた父親の記憶がよみがえってきて、もっと社会に貢献できる自分になろう!と気持ちを新たにしました。
=====================================================
埼玉県 Wさん(20 代・女性)
街頭での呼びかけなんて生まれて初めて。最初は緊張して声も出せず、看板を持って立ち尽くしていました。でも、駅前で人が大勢いても大声で呼びかける仲間の姿に背中を押されました。頑張って声をかけ続けた結果、5人の方が「献血したいです。場所どこですか」と言ってくれたんです。今後もこういう活動に参加し、自分が献血をするだけでなく、まわりの人に協力を呼びかけていきます。
=====================================================
東京都 Kさん(30 代・男性)
昨年、釈迦殿で開催された「献血のつどい」での街頭呼びかけの経験を生かして、今回はさらに長時間、多くの人に声をかけました。大型連休の繁華街は人通りが多い分、スルーされる割合も高くて途中で心が折れかけましたが、たくさんの人に協力してもらえたと聞き、何事もやり続ける大切さを実感しました。今回誘った友達は来られませんでしたが、これからも、あきらめずに誘い続けます。
=====================================================
京都府 Oさん(30 代・女性)
今日、初めて献血をしました。今まで、針を刺すとき痛そうだし、私1人がしたところで……と思っていたから。でも、日本赤十字社の方の講演を聞き、その1人の一歩が大事だと感じました。これからは、定期的に献血に協力したいです。また、私のように、何となくのイメージで献血を避けている人って結構多いはず。今回感じたことを、まわりの人に伝えていきます。
ママと子どもの笑顔が、地域を明るく!
【福島県】
福島の女性に元気になってもらうDAY!

| いろんな人とふれ合って、元気になってほしいから
福島県Myおせっかい推進委員長 菊池可南子さん 35歳
福島県の推進委員は、夫婦共働きで、子育て世代の女性が多いんです。そのまわりにも、仕事、家事、育児に追われ、余裕をなくしている女性が少なくありません。だから、みんなが日々の暮らしの中で感じていることを自由に話せて、明日からまた頑張ろうと思える場をつくりたいと、このつどいを企画しました。
どんな内容がいいか、青年だけでなく、子育て中の40代の推進委員にも相談しました。そして、ママたちが、忙しい合間を縫ってでも参加したい!と思えるような、親子で一緒に楽しめるつどいにしようと決まったんです。
男性の推進委員やパパたち、おばあちゃんたちがカレーを作り、子どもたちと妙一会の担当スタッフが一緒に遊んでくれている間に、私たちヤングミセスはつどい。じっくり話ができて、みんなスッキリした表情になりました。
つどいの後はみんなでカレーをおいしくいただきました。また、母の日が近いことにちなんでハーバリウム(※)作りをしながらの交流も……。参加して良かった!という声をたくさんいただけて、すごくうれしかったです。協力してくれたみなさんに感謝の気持ちでいっぱいです。
ママと子どもの笑顔が、家庭を明るくして、地域を明るくする。自分の会員や友人にも、もっとこういう場に出て、いろんな人とふれ合ってほしいと感じました。今後も福島県でいろんなつどいを企画していきます。
※ガラスの小びんにお花をオイル漬けしたもの。

◆ 参加者の声 ◆
| 悩んでいるのは私だけじゃないんだ
福島県 M・Kさん(30 代 女性)
義姉に誘われて、小学1年の息子と母と一緒に、久しぶりにつどいに参加しました。
息子は集団行動が苦手で、発達障がいがあるかもしれないとお医者さんから言われています。でも、ママ友には同じ境遇の人がいないから相談できず、親として心配が募るばかりでした。
その話をしたら、「うちの子もそうだよ」という小学3年生の子をもつお母さんがいたんです。いろんな話ができて、悩んでいるのは私だけじゃないんだって思えて……。すごく心強くて、頑張ろうって思いました。
息子も楽しかったようで、今日は来て良かったです。こういうつどいがあれば、また参加したいと思います。
すべての活動に、新しい仲間と参加しよう!

青年部部長 前田康喜
全国各地で青年を中心に、小さな子どもから親世代の人まで、みんなが自分たちの体を使って活動した「Ourおせっかいのつどい」。私もいくつかの会場に行かせていただき、共に行動する中で、同じ地域に暮らすいろんな世代が力を合わせ、地元の人たちに喜んでもらえる、社会に役立つ行いをする。これこそ、地域のつながりが薄れている今の時代に求められる、ほんまに大切な活動やなと感じました。
今回の活動を通して知ったように、世の中には、人の命や地球の未来にかかわる問題、社会のあり様が問われる課題が山積しています。また、個人に目を向ければ、仕事や人間関係、子育てなどの悩みを誰にも相談できず、1人で抱えている人がたくさんいます。
大切なことは、まわりの人の幸せを願い、社会で起きているさまざまな問題に対してアクションを起こす人を増やしていくために、すべての活動に、新しい仲間を誘って参加することだと思います。そこでつながった仲間と一緒につどいや弥勒山に参加して互いの心を磨き、人間が人間らしく生きていける、温かい世の中をつくっていく。それが霊友会青年部の社会貢献活動です。「Ourおせっかいのつどい」をきっかけにして、一緒に世の中をより良くしていきましょう!
<
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
>




