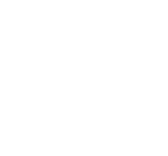 今月の
今月の
特集

2021.3.1
社会に目を向け 自分にできることを見つけよう
内閣府が全国の13歳~29歳を対象に行ったインターネット調査(令和元年11月1日~12月2日・有効回答者数10,982)によると、「社会のために役立ちたい」と回答した若者は70%だった。
人や社会の役に立ちたい 。そう思う若者は多い。でも、漠然としたその思いを、どうすれば形にできるだろうか 。2人の青年のエピソードから考えてみよう
①思いやりの心。子どもたちに 正しい「道」を伝えたい
会社員として働きながら、ボランティアで地域の小学生に剣道を教えているFさん。多忙な日々の中、どんな思いで剣道を教え続けているのか。子どもたちや保護者との関わりの中で、何を感じているのか。そして、Fさんの体験を通して見えてくるものとは―。
父が遺してくれたもの
ぼくの父は、代々続く地元の道場で、地域の小学生にボランティアで剣道を教えていました。そんな父のもとで、ぼくも小学2年生から剣道を始めました。すぐに夢中になり、練習にも一生懸命取り組むようになりました。
父は温厚な人でしたが、剣道ではとても厳しかった。あいさつを忘れたときなど、礼儀や礼節がなっていないときは、ものすごく叱られました。また、練習に取り組む姿勢を重視し、試合では仲間の出番のときも気を抜かず、全力で応援することを教えられました。
そんな父の教える剣道が大好きだったぼくは、高校を卒業した後、大学で剣道を続けながら、父のサポートをして一緒に子どもたちに教えるようになったんです。
ところがその4年後、Fさんが22歳のとき。父・Sさんは心臓の病気で亡くなってしまった。父親であると同時に剣道の師であったSさんの存在はFさんにとってあまりに大きく、とてつもない喪失感に襲われた。そんなとき、立ち直るきっかけをくれたのが霊友会の支部長だった。
うちは母が最初に霊友会に入会し、父も積極的に活動していました。そんな両親がいつもお世話になっていた支部長から、「真剣に霊友会の教えに取り組むことが、亡くなったお父さんへの何よりの親孝行だよ」と言われたんです。
ぼくはそれまでまったく霊友会の教えをやっていなかったんですが、親孝行になるならと、そこから真剣にやり始めました。毎日お経をあげる。毎月、支部の仲間と青年のつどいを開く。支部の仲間や担当者と一緒に、友達に「霊友会をやろう」と声をかけに行く。支部長に言われた通りに取り組んでみました。
同時に、父が代表をしていた道場をどうするかという問題がありました。一緒に教えてくれていた先生たちと相談し、ぼくが先頭に立たせてもらって、みんなで支え合っていこう! となりました。もちろんプレッシャーはありました。でも、父が遺してくれたものを、なんとか受け継いでいきたい。そんな思いだったんです。
しかし、どちらもうまく行きません。「霊友会をやろう」「つどいにおいでよ」といろんな人を誘うけど、断られる。剣道の教え子の保護者からは、まだまだ半人前の若造で指導がなっていないと思われ、「なんでうちの子を試合に出さないの」などと責められることも。父のように尊敬される人間には程遠い自分でした。

結果よりも大切なことがある
そんな中、父が亡くなった翌年に参加した「青年の弥勒山セミナー」が大きな転機になりました。人の役に立とうと一生懸命なみんなの姿に衝撃を受けたんです。ぼくは今まで自分のことで精いっぱいで、こんなに他人のことを真剣に思ったことはありませんでした。こんな仲間がたくさんいる霊友会ってすごい。ぼくもそんな人になりたい。友達を誘って一緒に活動したい。一緒に弥勒山に参加したい! そう思ったんです。
それからいろんな人に声をかけていきました。最初は断られてばかりで、何度もくじけそうになりました。でも、支部の仲間がいつも一緒に動いてくれて、あきらめずに頑張ろう!と励まし続けてくれたんです。どんなときも、悩みやうれしい気持ちを共有できる仲間の存在が力になって声をかけ続けることができました。そして、共に活動してくれる仲間の輪も、少しずつ広がっていったんです。
そうして霊友会の教えに取り組んでいく一方で、Fさんは、剣道を教える子どもたちのある姿が目に留まるようになった。
いつの頃からか、試合中に仲間の応援をしない子たちが多いなと感じるようになりました。自分の試合が終わると放心状態というか、ボーっとしている。保護者も、自分の子どものときだけ必死に応援していました。
ぼくが父から教わった剣道って、こういうものじゃなかったよな。父はきっと、剣道を通して、子どもたちが人のために動ける人間に育つことを願っていたんじゃないか。ぼくはそれをちゃんと伝えられていなかったんじゃないか。試合の結果より大切なことがある―。父から教わったことを子どもたちに伝えていくようにしました。
あいさつや礼儀作法を大切にする。練習中も相手を思いやり、学年が上がれば下の子の面倒をみる。試合では全力で仲間の応援をする。一つ一つ、ていねいに伝えていきました。良いことは良い、悪いことは悪いと毅然とした態度で接すると、子どもたちが少しずつ変わってきました。保護者も、そんなぼくのやり方に共感してくれる人が出てきたんです。
一人ひとりとちゃんと向き合い、人を思う大切さを伝えていけば、子どもたちの純粋な心はまっすぐ育つ。そんな子どもの成長を、保護者も喜んでくれる。そのことをFさんは実感した。

自分さえ良ければいい、という社会にはしたくない。未来を担う子どもたちがどう育っていくか、ぼくたち一人ひとりの手にかかっているんだなと思ったんです。
今、自分にできる社会貢献を
子どもたちだけでなく、保護者とも積極的にコミュニケーションを取るようにすると、剣道以外のことも話すようになりました。その中で、今から4年前、Mさんというシングルマザーの方が、長女の学校での人間関係や、長男の反抗期で悩んでいることを知ったんです。
霊友会の教えをやって、悩みを解決してもらいたい。そう思いながらも、強引に勧誘されたと騒ぎにでもなったら子どもたちに剣道を教えられなくなってしまう。ずっと霊友会の教えを伝えられずにいました。でも、ある弥勒山行事に参加したとき、人を思う仲間や支部長の話に心を打たれ、1年越しに勇気を出して教えを伝えたんです。Mさんは「やります」と言ってすぐに入会しました。
Mさんの子どもたちは、弥勒山やつどいでいろんな人と関わるのがとても楽しかったようです。そのおかげか、学校や家の中でも、明るく前向きに過ごせるように少しずつ変わっていきました。Mさん自身も、毎月つどいに参加する中で「霊友会の人たちはあったかい。なんでも親身になって聞いてくれる」と言いました。
今では、自分の子どもたちだけでなく、支部の仲間や周りの人たちのことを思って、お経をあげたり、声をかけたりと、ぼくと一緒に取り組んでくれます。
自分がしんどくても、支部の仲間や剣道の教え子たち、何より会員のことを思うと頑張れる。人として成長させてもらっているなと思うんです。
様々な問題をひとりで抱えていたり、何かに行き詰っている人が、まだまだたくさんいるかもしれない。社会に貢献するって言うと大げさに聞こえるかもしれないけど、子どもたちに思いやりの心を伝えていくこと、悩みや不安を抱える保護者の力になっていくことが、今、ぼくにできる社会貢献だと思います。「Myおせっかい」の精神で、これからもまわりの人と積極的に関わっていきます。
※写真はイメージです。本文の登場人物とは関係ありません。
②人と人が互いに支え合う。あったかい社会を目指して!
昨年、転職した平水利憲さん。新たに飛び込んだ世界で目にしたのは、様々な事情で困難を抱えている人たちと、社会の問題だった。世の中のために、私たち一人ひとりにできること、霊友会青年部が社会に貢献できることはなんだろう。平水さんの取り組みや実感を通して、一緒に考えてみたい。
 ※平水利憲さん
※平水利憲さん
生きづらさを 抱えている人たちの力になりたい
私は昨年の2月まで銀行員をしていました。10年以上ずっと営業部にいて、最後の2年間は人事部。人事部では、人事評価や昇格査定といった業務のほか、行員同士のトラブル対応やメンタルヘルスケアも担当しました。その中で、発達障がいのある行員が周囲の理解をなかなか得られず仕事がうまくいっていないなど、様々な事情で悩んでいる様子を目の当たりにしたんです。
その頃、私の会員と弟も仕事の悩みを抱えていました。会員は雇用契約期間が満了となった後、次の職場が見つからない。弟は体調を崩して仕事を辞めた後、次の一歩を踏み出せずにいたんです。
彼らに会うため、和歌山の実家に定期的に通い、一緒につどいをする中で、しんどかった彼らの気持ちも少しずつ前向きになっていきました。そして、いい職場にめぐり合えるようにと、修行に取り組みました。なかなか実家に総戒名を納められずにいた会員は、支部長の後押しもあり、納めることができました。弟は、弥勒山で決定(けつじょう)し、百日間の修行に取り組みました。そんな修行を通して、2人ともどんどん気持ちが前向きになり、それぞれ新しい職場にめぐり合うことができました。今では元気に仕事に行けるようにまでなったんです。
そんな2人の姿を見る中で、会員や弟のように、生きづらさを抱えている人たちの力になれる仕事をしたい。もっと自分に縁のある職場があるんじゃないか。そういう思いが強くなり、転職を決意したんです。
ほっとけない 人たちがたくさん!
夫婦で子育て真っ只中。そんな平水さんにとって、特に関心があったのが子どもにかかわる仕事だったという。そうしてめぐり合ったのが、あるNPO法人だった。
ここでは、「すべての家庭が安心して暮らせる社会」を目指して、発達障がいのある子どもたちの学習支援や、一人ひとりの子どもや家庭に寄り添う様々な支援を行っています。
虐待を受けた子どもたちや、親と一緒に暮らせない子どもたちが住める自立援助ホーム。子どもを預かるだけでなく、積極的に保護者をサポートする保育園。親子で一緒に地域交流ができるコミュニティカフェ。また、コロナ禍で不要不急の外出自粛が要請される中、SNSで気軽に悩み相談ができるサービスや、生活に困窮している家庭の子どもを対象にした無料の食料配布など、新たな事業も行ってきました。私もすべてが初体験で、分からないことだらけでしたが、少しでも役に立てるようにと頑張ってきました。
あっという間の1年を通して感じたのは、悩んでいることを周囲に相談できない人がたくさんいるんだなということです。
SNSでの相談サービスは、利用者の多くは未成年の学生。「寂しい」「話し相手がほしい」というものから、「居場所がなくてつらい」「家出しようかな」「死にたい」という相談も……。そして、共通しているのは、学校の先生や友達には「言えない」「言っても分かってもらえない」ということだったんです。
相談の中で学生の次に多いのが、子育て中のママたちだという。年齢にかかわらず、誰かの助けを必要としている人は決して少なくない。また、食料配布は、ある定時制高校の教師からの相談がきっかけだった。
その高校では、家計が苦しい家庭も多く、アルバイトをしながら学校に通ってる生徒が多いそうです。でも、高校生のアルバイトは飲食店が主。コロナ禍でアルバイトのシフトが減ってしまったり、アルバイト自体を辞めることになってしまい、満足に食事もできない生徒が多いと、その先生から教えられました。
そこで、高校の近くまで行き食料配布をするようになりましたが、最初は遠くから見ているだけの子も多かったんです。きっとまわりの目を気にしてしまったり、自分の家の問題だからと、私たちに頼ることに引け目を感じていたんじゃないでしょうか。どうしたのかなと思い、こちらから声をかけに行くと、喜んで受け取って帰ってくれました。
そんな様々な実態を目の当たりにしてきたことで、世の中にはほっとけない人たちがたくさんいるんだという思いが、より一層強くなりました。
世の中の役に 立つ活動を
自分の友達や身近な人の中にも、人知れず悩みや不安を抱えている人がまだまだいるかもしれない。そんな人たちの力になれることは何かないかと考えていると、ふと気づいたことがあったんです。
例えば、うちの法人でやっているコミュニティカフェ。これは、民家の広間を借りて、子連れのママたちがそこに来て、子どもは遊ぶ。ママたちは交流もできるし、子育ての悩みや不安を吐き出せるというものです。これって、霊友会の「つどい」そのままなんですよね。私たち霊友会の会員が日頃からやっている活動も、世の中の役に立てる活動なんだとあらためて気づけたし、だからこそ、もっと広げていきたいという気持ちになりました。
 ※写真はイメージです。本文の登場人物とは関係ありません。
※写真はイメージです。本文の登場人物とは関係ありません。
今年、青年部は、「ほっとかない!ほっとけない!となりの人から世界まで」をスローガンに掲げている。一人ひとりの「ほっとけない」気持ちを大切にし、身近な人から、社会の問題にまで目を向けることこそ大事な役割だ。
昨年の暮れ、先端支部でオンラインのつどいをしました。そこで、20年一緒に活動している会員が、つらい気持ちを打ち明けてくれました。仕事の関係で一人暮らしをすることになったが、コロナ禍で外出もままならない。職場と家の往復だけの毎日に孤独を感じ、仕事もうまくいかなくなっている、と。
すると先端支部の仲間が次々と彼に声をかけました。「今だったらオンラインでつながれるから、毎週でもつどいができるよ!」「一緒にやろう!」。そして、会員のいる名古屋、先端支部のある和歌山、私のいる千葉をオンラインでつないで、たくさんつどいをするようになったんです。おかげでその会員も元気になり、今は前向きに仕事に取り組んでいます。
 ※会員や支部の仲間とのオンラインつどいは、自分も元気をもらえる
※会員や支部の仲間とのオンラインつどいは、自分も元気をもらえる
離れていても、何かあったらすぐ力になれる。お互いに支え合っていける。そんなあったかい関係を築いていける霊友会の仲間の輪をもっと広げたいと思いました。まわりの人をもっと元気にしていけるよう、世の中の役に立つ活動を広めていけるよう、仕事にも、霊友会の活動にも、全力で取り組んでいきます。
<
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
>




