- TOP>
- ボランティア一覧
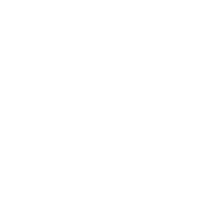 REIYUKAIボランティア
REIYUKAIボランティア

REIYUKAI
ボランティア
2025.3.1
耳の不自由な人と話し手の架け橋になる。
パソコン要約筆記に挑戦!

霊友会福祉センターの栗原さん(中央奥)、泉本さん(左奥)のアドバイスを受け、要約筆記に挑む
多様な人と人が関わり合って生きている現代社会。どんな人も安心して暮らせる世の中をつくるためには、さまざまな取り組みが必要です。その1つが「情報保障」。障がいによって必要な情報を得ることが困難な人に対して、代替手段を用いて情報を提供することです。
今回は、聴覚障がい者に対する情報保障の手段である「要約筆記」にフォーカス。要約筆記って? どうして必要とされているの? その答えを探るため、青年部副部長の野口晃輔さんが、霊友会福祉センターの栗原慎介さんと泉本佳子さんに突撃。要約筆記の体験もしてもらいました!

青年部副部長 野口晃輔「私が体験しました!」
野口 はじめに、要約筆記とはどういうものなのか教えてください。
栗原 聴覚に障がいのある人のために、話された内容をその場で要約して文字で伝える方法を要約筆記と言います。でも、一般的にはあまり知られていないんですよね。聴覚に障がいのある人とコミュニケーションを取る手段と言われてまず浮かぶのは、筆談や手話じゃないですか?
野口 そうですね。大学の同級生で聴覚に障がいのある友達がいますが、大学時代は筆談で会話していました。最近では、スマホも活用してやり取りしています。
栗原 筆談は1対1やごく少数ならいいんですが、例えば、一定数の人に向けて、複数の人が次々と発言する会議などの場。また、発言者は1人でも、連続して何分も話す場面だとどうでしょう。霊友会の行事で言えば、つどいや弥勒山で参加者が発表するときや、登壇者が話す場面などがそうですね。
野口 筆談だと難しいですね……。
栗原 手話は、生まれつき聴覚に障がいがある人のほとんどは習得しますが、病気や事故などで聴力を失った人は、手話を習得していない人も多い。また、手話通訳を利用される際に、より正確に内容を把握するために要約筆記を同時に利用するケースもあります。
そんな人たちのために、要約筆記が必要なんです。病院や役所、学校……他にも色々な場面で、専門的な資格をもつ「要約筆記者」として活躍している人が世の中にいるんですよ。
野口 そうなんですね! ますます興味が湧いてきました。では実際に、どうやって文字に変換するんでしょうか。
泉本 要約筆記の手法には大きく分けて「手書き」と「パソコン」があります。手書きは、ノートやホワイトボードに書いた文字を見せたり、OHP(文字や図表をスクリーンに投影する装置)を使う手法。パソコンは、キーボードで打ち込んだ文字を、モニターなどに表示します。1人でやることも、数人でやることもあり、利用される側の人数や要望、会場の環境などによっても細かな点は変わってきます。
栗原 では基本的な説明はこれくらいにして、早速体験してみましょう!
野口 え、もうやるんですか!? が、頑張ります……!
今回挑戦するのはパソコン要約筆記。使うのは、毎月先端支部に届けられるDVD『いい顔に会いたい』に収録されている体験発表の映像だ。①映像を流して音声を聞きながら、②キーボードで文字を打ち込むと、③専用ソフトを通じてモニターに文字が表示されるという流れ(下記参照)。野口さん→栗原さん→泉本さんの順番で、ある程度の文字数を打ったら、その続きから次の人が打ち、それを繰り返すというルールを決め、いざスタート!

「カタ、カタカタ、カタカタカタ…」。無機質なタイピング音がこだまする室内。序盤は順調に見えたものの、次第に打ち間違いが多発する野口さん。「あ!」「うわっ!」「ごめんなさい!」。こうして、初挑戦の10分間が過ぎていった。
| 大切なのは、話し手の言いたいことが相手に伝わるかどうか
野口 ふぅ……。
栗原 どうでしたか?
野口 いやあ、難しいです。話すスピードに追いつけなくて、焦っちゃいます。
栗原 それを実感してもらいたくて、いきなり挑戦してもらったんです。野口さんは今、話し手が発する言葉を、すべて文字にしようと頑張ってくれましたよね。でも、どんなに熟練の人でも、長時間、一字一句を正確に変換し続けるのはほぼ不可能。というか、その必要はないんです。
野口 どういうことですか?
栗原 要約筆記のポイントは“要約”です。「あー」や「えっと」などの無駄な言葉はどんどん省く。そして、例えば「その彼は、高校1年生のときに出会って、かれこれ10年くらいの付き合いになる、出会ってからずっと仲のいい、私にとって一番の友人です」と話された場合。一旦そこまで聞き終えてから、「彼は高1からの10年来の親友です」でOK。話をよく聞いて、上手に要点をまとめれば、2~3割の文字数でも伝えることができるんです。
野口 なるほど……。だから栗原さんと泉本さんは、少し話を聞いてから打ち始めても余裕があったんですね。
泉本 先ほど、野口さんのパソコンの画面上にも、私たちが打っている文字がリアルタイムで表示されていましたよね。これが専用ソフトを使用するパソコン要約筆記の特徴です。1人で頑張ろうとせずに、他の人の状況も見ながらお互いに助け合うのがコツ。「私、○○から打ちますね」と声をかけ合ってもいいですね。最初は難しいと感じるかもしれませんが、慣れてくればお互いにタイミングが何となく分かるようになり、うまくバトンタッチできるようになりますよ。
栗原 大切なのは、話し手の言いたいことが相手に伝わるかどうか。要約筆記は、あくまでもその手段の1つに過ぎないということをぜひ覚えておいてください。では、そのことを踏まえて、もう一度チャレンジしてみましょう!
次も同じく『いい顔に会いたい』収録映像の中から、先ほどよりも話し手のスピードが速い体験発表の要約筆記に挑戦。すると、難易度が上がったにもかかわらず、先ほどのアドバイスが生かされ、格段にスムーズになった野口さん。充実した表情で、体験を終えた。
野口 ありがとうございました! うまくバトンタッチできた瞬間は、これぞチームプレー!って感じで、なんか気持ち良かったです。
栗原 すごく上手でしたよ。霊友会では、毎年春と夏に開催している弥勒山「三者のつどい」などの行事でパソコン要約筆記のボランティアを募っていますが、野口さんは即戦力です! ぜひお待ちしています。
野口 本当ですか!? でも、資格が必要なんじゃないですか?
泉本 いえ、霊友会で募集しているボランティアは、簡単なパソコンの操作ができれば、資格は必要ありません。ちょっとしたスキルを生かしてみたい、誰かの役に立ちたいなど、どんなきっかけでも大丈夫です。
弥勒山をはじめ、「三者」の活動で大切にされているのは、障がいのある人、その家族・介護者・介助者、ボランティアの三者が、お互いを尊重し、足りないところを補い合いながら、みんなで支え合ってつくるということ。経験者や私たち職員がサポートしますので、安心して多くの人に挑戦してほしいと思います。

野口 分かりました! 今回体験させてもらってすごく楽しかったですし、学びもありました。特に、“要約”の大切さ。普段、仕事で会議の議事録などを作ることがあるんですが、要点は何か、大事なことは何かをとらえ、簡潔な言葉にするトレーニングにもなると実感しました。
私も今年の弥勒山「三者のつどい」でパソコン要約筆記のボランティアに挑戦しようと思うので、読者のみなさんも、ぜひ応募してみてください!
要約筆記のボランティア参加希望の方、詳細をお知りになりたい方は下の「パソコン要約筆記 キミにもできる!ボランティア大募集!」にアクセスしてください。
またオンライン手話講習会参加者も募集しています。受講希望の方、詳細をお知りになりたい方は下の「オンライン手話講習会参加者募集中!」にアクセスしてください。




