- TOP>
- ボランティア一覧
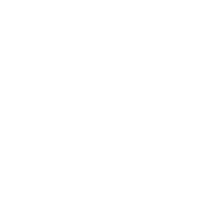 REIYUKAIボランティア
REIYUKAIボランティア

REIYUKAI
ボランティア
2025.4.1
地域社会の一員として
みんなをパンで笑顔に
NPO法人Csクリエーション地域活動支援センター「コスモスの家」

「ありがとう こだま 基金」は、施設の修繕やパンをこねる機械の購入などに役立てられている
=====================================================
香川県丸亀市にあるNPO法人Csクリエーションが運営する地域活動支援センター「コスモスの家」。その由来は、精神障がいのある人の居場所づくりを目的に、障がいのある人の家族有志が立ち上げた家族会が平成元年(1989)に共同作業所を開いたことに始まる。その後、家族会の高齢化に伴い、運営は新設したNPO法人に引き継がれる。徐々に活動の幅を広げ、25年前に利用者の社会的自立を目指し、パン事業をスタート。今ではみんなを笑顔にするパンとして地域の人々に愛されている。
=====================================================
| コスモスの家はコミュニティーの一員
霊友会との交流は、平成22年(2010)に香川県高松市で開催された「創立祭2010」で、パンの販売でブースを出したのが始まりだった。最近では去年10月の「三者・生き方フェスティバル」へ出店。「コスモスの家のみなさんがつくる美味しいお弁当を食べたい」というスタッフからの発注もあった。
コスモスの家は法人化してから20年以上。この地域で障がいのある人が社会の中へ踏み出していく、先駆けとなる施設だったという。コスモスの家が大切にしていることとは何だろうか。
コスモスの家の所長を務める宮武陽子所長(45歳)に、現在の活動や理念について聞いた。
私たちが一番大事にしていることは、人とのふれあいです。「自分たちの手で自らパンを届ける」ことをモットーにして、地元のみなさんとの交流を積極的に行ってきました。市町村の役場や地域の企業で働く人たちへパンをお届けしたり、高齢者施設への納品、歩くのが不自由な高齢者の個人宅への配達なども行っています。

地域に根づいた運営をモットーにするコスモスの家
おかげで施設に直接ボランティアに来てくださる方もいれば、利用者さんと一緒に料理を作ってくださったり、採れた野菜のおすそ分けをいただいたりなど、日ごろから温かく見守っていただいています。
| 利用者の経済的自立のために“おせっかい”
施設には22歳の若者から63歳の年配者まで、幅広い年齢層の人が通所している。20代の若い世代は、これから社会に出ていくために必要なことをトレーニングする場として活用しているケースが多い。63歳の利用者は、施設でみんなとご飯を食べたり会話を楽しみ、自分の居場所として利用している。今後の施設の在り方について、宮武さんは明るい表情で次のように語る。
40年近く前に家族会として立ち上がった当初の理念である「居場所づくり」が、しっかり今も受け継がれています。当初はつくったパンの形がいびつになってしまうなどの失敗も多々ありましたが、今ではすべての工程で利用者が中心となって運営できています。 今後の目標は、利用者に周りの人たちと良好な関係を築いてもらうことと、社会の中で生きていくために必要な経済力を身につけてもらうことです。

職員の田中雄喜さん(39歳)。一人ひとりの個性に寄り添いながら、安心してチャレンジできる環境を提供
利用者の経済的自立のために、雇用の働きかけにも積極的だ。うどん屋さんで人手が足りないと聞けば、利用者とお店側とのパイプ役になって調整することもあるという。
これは私たちの仕事の範囲を超えるものではありますが、初めはためらっていた利用者さんでも、「やってみたらええやん」と私たちが背中を押すことで意外とすんなりできたりします。こういう“おせっかい”が大切だと感じることが多々あります。
| 何かをしてもらうより「何かをしたい!」
宮武さんは、霊友会との今後の展望を次のように話す。
施設の利用者が何よりも喜ぶことは、「何かをされること」以上に、「自分たちが何かをすること」です。たとえば、霊友会のみなさんにパン教室でパンのつくり方を教える機会などがあると良いですね。
福祉の現場では、基本的に何かをしてもらうケースが多いのですが、パン教室では自発的に「何かをしたい!」と思える関わり方を霊友会のみなさんともてることによって、本人たちの大きな自信につながると思うのです。
「人のために何かできた」「誰かの役に立てた」という体験は、利用者が社会で生きていくうえでの宝物になります。パンづくりを通じて、施設以外の他者との関わりをもつ素晴らしい機会にもなります。霊友会のみなさんと一緒に何かをつくることは、「障がいのある人と地域社会との共生」という私たちの理念そのものだと思います。

パン作りを通じて得た経験が、利用者の成長につながる
これからもご支援を賜りながら、利用者の自立と、より美味しいパンづくりの研鑽を積んで、地域のみなさんを笑顔にしていきたいと思います。




